なんかうまくいかない…
そんなときありますよね。
そんなときに、神社にお参りに行くという方も多いはず。
期間限定のお手軽に厄除けできる神事「茅の輪くぐり」をご紹介します。
茅の輪くぐりとは?
年に一度神社に現れるこんなもの、見たことありませんか?

これは「茅の輪」と呼ばれるもので、これをくぐり、無病息災を願うことを「茅の輪くぐり」といいます。
参道の鳥居などの結界に、茅(ちがや)という草で編んだ輪を作りこの輪をくぐることで心身を清め災厄を祓い、無病息災を願います。
ただくぐるだけでなく、くぐり方もあるので、ご紹介していきます。
茅の輪のくぐり方
今から紹介するくぐり方は一般的なものです。
神社によって異なるものですので、記載がある場合はその方法をお試しください。
また、混雑時には”くぐるだけ”でもよいとされています。

一般的なものは、唱え詞を唱えながら、∞の字の形に3回くぐり抜けるというものです。
①正面でお辞儀、左足でまたぎ、左を通って正面へ
②正面でお辞儀、右足でまたぎ、右を通って正面へ
③正面でお辞儀、左足でまたぎ、左を通って正面へ
④正面でお辞儀、左足でまたぎ、参拝へ

唱え詞はより深く茅の輪くぐりをしたい方向けです。
くぐるときに唱えたり、心の中で念じたりします。
唱え詞で代表的なものは
「祓い給へ 清め給へ 守り給へ 幸え給へ」
(はらへたまへ きよめたまへ まもりたまへ さきはえたまへ)
(訳:お祓いください、お清めください、お守りください、幸福をお与えください。)
祝詞の一種で「略拝詞(りゃくはいし)」と呼ばれます。
神様に対し、お祓いとお力添えを願っています。
地域や各神社で異なることがありますので、唱え詞を言われる際には確認ください。
茅の輪の近くに掲示してあることが多いですが、もし掲示されていないようでしたら、上記の略拝詞を唱えましょう。
1周目~3周目まで、すべて異なる場合もあるそうですよ!
茅の輪くぐりの注意点
くぐることで”心身を清め、災厄を祓い、無病息災を願う”茅の輪くぐり。
絶対にしてはいけない行為があります。
それは「茅を引き抜き持ち帰る」こと。
絶対にしてはいけません。
茅の輪くぐりは、くぐることによって
・心身を清める=穢れを落とす
・災厄を祓う =災厄を落とす
ことができます。
落とされた穢れや災厄は…?
これは茅に移されていきます。
その茅を持ち帰るということは、穢れや災厄を持ち帰るのと同義となるのです。
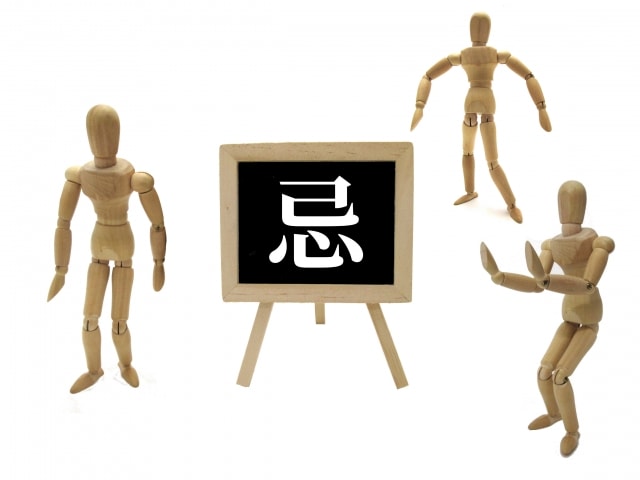
茅の輪くぐりはいつ?
茅の輪を目にするのは6月~7月頃。
これは茅の輪くぐりが、毎年6月30日に各地の神社で執り行われる「夏越の祓(なごしのはらえ)」の儀式のひとつだからです。
しかし、あまりに定着され、茅の輪くぐり=夏越の祓というイメージもあるくらいです。
神社によって茅の輪が設置されている時期は異なりますが、6月~7月にかけて設置されている神社が多いようです。
夏越の祓 ってなに?
茅の輪くぐりが儀式のひとつである、夏越の祓。
これは大祓と呼ばれる神事です。
大祓とは、日常生活の中で知らず知らずに犯した罪や過ち心身の穢れを身代わりとなる人形に託し祓い清める神事のこと。

- 6月の晦日(30日)が夏越の祓
- 12月の晦日(31日)が年越の祓
半年ごとに、穢れや災厄を落とす神事が風習として日本にはあったのです。
夏越の祓は、「祓い清めの慣わしで心も身体も清々しく夏を迎える神事」
年越の祓は、「1年を無事に過ごせた感謝と新しい年を清らかに心で迎える神事」
人は日常の中で、穢れをもっているということですね。
知らないうちについてしまった穢れや災厄を半年に一度、清めましょう。
茅の輪くぐりはくぐるだけで清められるのでチャレンジしやすい儀式といえますね。
茅の輪くぐりの由来
茅の輪くぐりの由来は、日本神話。
スサノオノミコトが旅の途中に宿を借りようとしたところ、お金持ちの兄”巨旦将来”は貸してくれず、その弟である”蘇民将来”は貧しいながらも宿を貸してくれ、精一杯のおもてなしをしてくれました。
旅先からの帰り道、スサノオノミコトはおもてなしをしてくれた蘇民将来の一家に「わたしは神だ。今後災厄を避けるためには“蘇民将来の子孫である”と言って地血の輪をつけなさい。」と進言をします。
すると、その日の夜に疫病が流行り、この一家以外の村人は死んでしまいました。
しかし、茅の輪を身に着けていた蘇民将来の一家は難を逃れました。
この神話を基に、茅の輪が無病息災を祈願するものとなったのです。
それまでは茅の輪を神話の通りに腰につけていましたが、江戸時代を迎える頃には、現在のようなくぐる形になったといわれています。
茅の輪だけでなく、お守りや護符に“蘇民将来子孫之家門”“蘇民将来子孫也”といった文言があります。
これも神話を基にした厄除のひとつです。

時期ですが、この6月の時期は梅雨の影響もあってか、疫病が流行る時期でした。
病気は「穢れが呼び込むこと」と考えていた古来の人々が、穢れを払う儀式を行うようになったといわれいます。
おわりに
茅の輪くぐりは夏越の祓の行事のひとつですが、神社によっては冬の年越の祓でも行われるところもあります。
そういった場合でも作法は同じですので、ぜひ半年分の穢れを移していってください。
作法が分からないから、と敬遠するのではなく、ぜひ古来より伝わる風習に挑戦してみてください☺
スッキリするかもしれませんよ。
-

-
【兵庫県淡路島|イザナギ神社】どんな神社?ご利益、歴史、見どころ・・・
瀬戸内海に浮かぶ淡路島。 その淡路島の中間ほどにあるのが「伊弉諾(イザナギ)神宮」。 神様のトップと呼ばれる天照大神の父、イザナギの名のつくこの神社。 一体どんな神社なのでしょうか?どん ...
続きを見る


